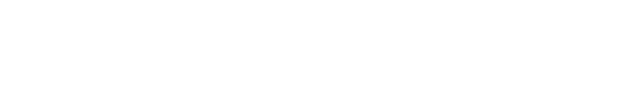病気症状について
診療設備及び可能な検査
- 純音聴力検査
- ティンパノグラム
- 内耳機能検査
- 平衡機能検査
- 重心動揺検査
- 簡易睡眠時無呼吸検査
- 溶連菌迅速検査
- インフルエンザ迅速検査
- 炭酸ガスレーザー
- OAE(誘発耳音響放射)
- アデノウイルス迅速検査
- ビデオ鼻咽喉スコープシステム
特色とする治療法など
悪性疾患の早期発見の為にビデオスコープを使った内視鏡検査を行っています。
小児の難聴特に通常検査の困難な2歳以下の小児例においても誘発耳音響放射等にて難聴のレベルを推定しております。
これまで入院での検査が必要とされた睡眠時無呼吸症候群の検査を最新の機器の導入により通院で行っております。
鼻アレルギーの予防的レーザー治療は早期より導入しこれまで1000症例以上の施行例があります。
ダニ・スギ花粉に対する舌下免疫療法(減感作療法)を導入しております。
耳鳴り・めまい・嗅覚異常・咽喉頭異常感症の方に対して漢方薬での治療を積極的に導入しており、特に耳鳴りの苦痛な方にTRT療法(耳鳴りの順応療法)を導入しております。
また難聴の方に対して定期的に補聴器外来(月に2回程度)を行っております。
メニュー
急性中耳炎
急性中耳炎とは?
中耳に感染を起こした状態で、主に細菌が中耳に入り込んで起こり侵入経路はほとんどが耳管からです。
耳管は中耳と鼻の奥つないでいる長さ約3cmのトンネルで普段は閉じていますが、つばをのみ込んだり、あくびをした時に瞬間的に開き、中耳内の気圧が外圧と等しくなるよう”調節弁”の役目をしています。
鼻とつながっていることより耳管は鼻汁中の細菌に侵されやすい場所になっています。
どんな時に起きる?
ほとんどが風邪をきっかけに起こり、鼻やのどの炎症が耳管を通って中耳にいきます。特に子供の耳管は大人より太くて短いので炎症が起こりやすくなります。
また鼻炎・副鼻腔炎にかかっている時にも起こりやすくなります。
どんな症状?
耳の痛みが徐々に強まり、ズキンズキンと脈打つようになります。
乳幼児では痛みを訴えなくても不機嫌になり、激しく泣いて手で耳の周りを触ったりします。
38℃以上の高熱を伴うこともあります。耳鳴りや耳のつまった感じがして聞こえにくくなります。
時には中耳に貯まった膿が鼓膜を破り、耳だれとして出てくることもあります。
どんな治療が必要?
治療の第一は安静と抗生物質その他の薬を正しく服用することです。
全身の状態および鼓膜の状態によっては鼓膜切開が必要な場合あります。
またある程度炎症が治まれば聴力の確認と耳管の通りをよくするため耳管通気を行うことが重要です。
再々急性中耳炎を繰り返す場合は免疫力の低下が下地になっていることもあります。
どんな予防が必要?
手軽に予防法としては、うがい・手洗いを励行して風邪を引かないようにすることです。
乳幼児では鼓膜の状態がよくなった後も約1ヶ月くらいはちょっとした風邪でも再発する恐れがあるので注意が必要です。
鼻のかみ方大事です。片方ずつゆっくりかみようにしましょう。
入浴については熱がなければ差し支えありませんが、頭を洗う時、耳・鼻から水が入らないようにしましょう。
滲出性中耳炎
滲出性中耳炎とは?
いろいろな原因により中耳腔に貯留液がたまる病気です。
貯留液の粘調度はさまざまです。
本来中耳と鼻は耳管という管によってつながっており中耳腔の貯留液はこの管を介して排出されるのですが耳管を開通させない鼻やのどの病変(鼻副鼻腔炎・アデノイド・腫瘍など)もしくは中耳腔の貯留液が粘調すぎて排出されにくくなることが原因と言われています。
中耳に液がたまる原因としては急性中耳炎の反復やアレルギー体質などが考えられています。
どんな症状が起こるか?
中耳に浸出液がたまることにより、鼓膜からの音の刺激が内耳の神経に伝わりにくくなり難聴を感じたり耳内に圧迫感やふさがった感じを自覚します。
小児では軽症の場 合見逃されることが少なくありません。
急性中耳炎を繰り返したり耳を気にしてよくさわったりするなどの症状があれば一応滲出性中耳炎の存在を疑う必要があります。
どんな治療が必要か?
滲出性中耳炎の診断は鼓膜の状態の観察により比較的容易ですが聞こえの検査や鼓膜の可動性の検査も参考になります。
治療としては浸出液の吸収のために鼻から耳管・中耳に空気を送る治療(耳管通気といいます)をしますが貯留液が粘調すぎる場合は鼓膜の切開を行い直接排液を必要とすることもあります。
難治性の場合には鼓膜切開孔より中耳腔に細いチューブを入れて持続的な換気を行うこともあります。
以上の他に鼻副鼻腔炎やアレルギー体質に対する治療も重要であります。
当院では3歳以下では自然治癒傾向が多いことを考慮し鼓膜切開等の外科的治療はできるだけ避けています。
4歳以上では耳管通気等の保存的な治療が主体ですが、病変が高度な時は鼓膜切開をすることもあります。
10歳以上の難治例では成人と併せて鼓膜切開やチューブ留置術等の治療を勧めています。
アデノイド
アデノイドとは?
鼻腔後部の咽頭後壁(のどの奥の上)に位置するリンパ組織です。
扁桃(へんとう)もアデノイドも生下時には小さいですが、次第に生理的に肥大し、アデノイドは3~7歳で最も発育します。
扁桃・アデノイドともに感染によりさらに肥大しますが8~12歳以降は両者ともに次第に縮小し、アデノイドは思春期にはほとんど消失します。
アデノイドによる症状は?
(1)鼻症状
アデノイドが鼻腔後壁を閉じるため鼻づまりが起こります。
鼻粘膜の慢性炎症・分泌 過多がみられます。
このため副鼻腔炎や気管支炎の原因になることもあります。
鼻づまりによる口呼吸のため鼻声・発音の不明瞭が生じることがあります。
(2)耳症状
アデノイドが耳管と咽頭の開口部を圧迫したり閉塞することにより耳管カタル・滲出性中耳炎を起こします。
また慢性炎症のあるアデノイドから耳管経由で中耳に感染が及んで急性中耳炎を起こします。
中耳炎の反復により難聴・言葉の後れが起こることがあります。
(3)呼吸症状
鼻呼吸が妨げられるため、著明ないびき・睡眠呼吸障害が生じることがあります。
また慢性的な頭痛を訴えることもあります。
どんな治療を行いますか?
まず鼻咽頭処置・ネブライザー療法等の保存療法を行いますが上記の症状のコントロールが困難な場合アデノイド切除術(入院が必要)を行います。
慢性扁桃炎
慢性扁桃炎とは?
扁桃の急性炎症が完全に治癒せず、扁桃の陰か(扁桃の表面にみられるくぼみ)や実質に炎症性病変が残っているもので、急性炎症を反復するものを習慣性扁桃炎と呼びます。
また扁桃周囲に炎症が拡がったものを扁桃周囲膿瘍といいます。
どんな症状ですか?
通常は咽頭の異和感・乾燥感等ですが比較的軽度です。
急性増悪時には発熱・陰頭痛・嚥下痛・耳への放散痛を伴います。
特に扁桃周囲膿瘍を発症しますと食事をとることが困難になり全身衰弱をきたします。
どんな治療を行いますか?
含嗽に加えて十分な睡眠・規則的な生活を送ることが大事ですが急性時には抗生物質の内服(場合によっては点滴)と安静臥床が必要です。
ただし以上のような保存療法で治療効果が期待できない場合手術療法(扁桃摘出術)が必要になります。
どんな方に手術が必要ですか?
- 1年に4-5回以上急性の炎症を繰り返す。
- 保存的な治療に抵抗する慢性的な痛みや微熱がある。
- 扁桃肥大のため摂食・嚥下・睡眠呼吸に障害がある。
- 扁桃周囲膿瘍を繰り返す。
- 扁桃に腫瘍が疑われる。
- 扁桃から離れた諸臓器に二次性の障害がある。(病巣感染症といいます)
二次疾患としてはIgA腎症・掌跡膿疱症・関節リューマチ・胸肋鎖骨過形成症などがあります。
最近扁桃指数という考えがあります。
扁桃指数=(1年間の扁桃炎の罹患回数)*(罹患年数)
概ね8以上であれば扁桃を摘出した方が医学的にも社会的にもよいというデータがあります。
扁桃炎を繰り返す扁桃は免疫機能が低下しており、摘出による免疫能の低下は否定されています。
昔の考えにとらわれない方がよいと思います。
慢性副鼻腔炎
慢性副鼻腔炎とは?
鼻腔・副鼻腔に慢性的な炎症を起こした状態です。
鼻腔というのは鼻の穴からのどまでの空間ですが、鼻腔の周囲にあるいくつかの小部屋(空洞)を副鼻腔といいます。
副鼻腔は鼻内の乾燥を防いだり等の役割があり細い通路にて鼻腔とつながっています。
鼻腔・副鼻腔ともに粘膜に覆われており表面にある織毛という細胞にて鼻汁を排泄できるようになっています。
風邪などを契機に鼻腔に細菌感染が起こり、鼻内の炎症が副鼻腔に波及すると粘膜の腫脹や多量の鼻漏により織毛の機能が妨げられ、組織が障害されるとともに鼻汁の排泄される通路が妨げられた状態を副鼻腔炎といいます。
体質的な問題(感染をおこしやすい等)・鼻腔の骨格の問題(鼻中隔弯曲等)・アレルギー性鼻炎などがあると副鼻腔炎が慢性化した状態になり、これを慢性副鼻腔炎といいます。
どんな症状ですか?
鼻汁・鼻づまり・頭が重い・臭いがわからない等です。
また鼻汁がのどに流れることにより痰がからんだ咳が出たりすることもあります。
小児の場合鼻汁により鼻腔が閉塞されて滲出性中耳炎の原因となることもあります。
どんな治療を行いますか?
局所の治療としては、鼻汁の吸引・ネブライザ療法等を定期的に行います。
また薬物療法として抗生物質・粘液修復財・消炎酵素剤・血管収縮剤等の投与を行います。
最近ではある種の抗生物質の長期少量投与(マクロライド療法)等も行います。
ただ局所の粘膜病変が非常に強い場合(ポリープがある場合・鼻中隔の高度の弯曲等)は内視鏡手術が必要な場合があります。